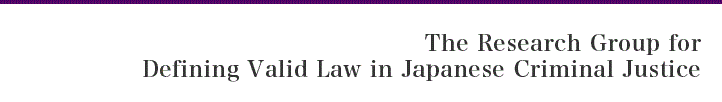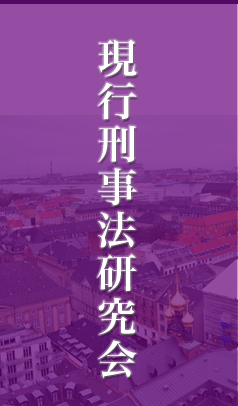研究会趣旨・会長挨拶

我が国の刑事法学では、現在、理論刑法学・刑訴法学が非常に発展しており、論者の考える理論を示すことによって、個別の論点を解決する方法が主流となっています。そして、それが極端になる場合には、実務において現実に行われている判断とはまったく異なる思考枠組に基づくまったく異なる結論が導かれることもあります。しかし、裁判所における判断が、現に社会において果たしている機能に鑑みると、裁判所の判断自体がひとつの「法」を形成し、社会を統制しているのであって、これを無視することはできません。裁判所の判断を前提としつつ、刑事法に関する解釈論を考えていく必要があるところです。
従来、この「法」にアプローチするには、判例の文言を中心として分析し、自己の立場から批判的検討を加える「判例『評釈』」が通常の方法でした。しかし、これでは、判例の背後にある裁判官の本当の思考が明らかにされず、また、判例を理論的に整理するにしても、自己のよってたつ理論体系から、というバイアスのかかった形での整理しかできないこととなります。従来の刑事法学の目的が、論者の意図する理論の体系を構築することにあるのだとすれば、それで問題はないとも言えましょう。しかし、前述のような立場に立つのであれば、より客観的な方法でアプローチし、「現」に「効」力を有している「法」を把握する必要があるように思われます。
私たちは、この研究会により、実際に「法」を形成する役割を担っている裁判官の思考――それには、意識的なものもあれば無意識的なものも含まれます――を、推測も含めて、言語化・理論化・体系化することを試みたいと考えています。このアプローチは、①判例に現れた文言ではなく裁判官の思考そのものを対象としてアプローチする点、②自己の理論体系からの外在的な批判ではなく、裁判官の思考に内在する事実を汲み取ろうとする点で、従来の一般的な判例「評釈」とは決定的に異なります。
以上の目標のもと、研究会を開催しておりますが、新しい試みですので、試行錯誤の面もあります。この研究会のHPを通じて、研究成果を発信するとともに、皆様からのご意見、ご指導を賜れれば幸いです。
平成24年4月
会長 松澤 伸
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(追記)
本会会長松澤伸を研究代表者とする共同研究「裁判官と研究者の協働作業による我が国の現に行われている刑事法理論の研究」(一般財団法人司法協会より平成22年度~25年度研究助成)の実施は、本会における研究会をその母体としております。ここに記し、司法協会の助成に心より感謝申し上げます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・